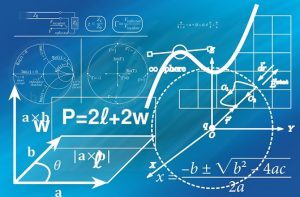大学入試改革の4つの変更点
高校での試験方法が変わる
大学入試改革は高校教育改革でもある
大学入試が変わるということは、大学入試のための勉強をする高校の教育も必然的に変わらなければなりません。
そこで、高校では、各学校独自のテストで学力を測るのではなく、
「高校生のための学びの基礎診断(仮称)」で多面的な評価が同じ基準でできるよう検討されています。
CBTの活用
CBTとは「Computer Based Testing」の略で、コンピュータを利用した試験方式です。
受験者はコンピュータに表示された試験問題に、マウスやキーボードを使って解答します。
文章だけでなく、画像・音声などさまざまな問題をデジタル化し、データベースで管理するので、
多彩な出題パターンが設定できます。
試験問題は受験者ごとに異なり、その都度問題データベースから適切に組み合わされて出題されるので、
同じ会場で同じ時間に受験しても受験者ごとに異なる試験問題を受けることができます。
ただ、今はまだ専門的・技術的に研究・検討を行わなければならないので、すぐに導入するというわけではなさそうです。
当面は紙による実施となりそうですが、研究が進めば、
スマートフォンやタブレットで試験を受けることも可能になるかもしれません。
IRTの活用
IRT(項目反応理論/項目応答理論)とは、学力を数値化する測定理論です。
今までであれば、Aテストの60点とBテストの80点は、両方結果が数値で現れていますが、
問題そのものが異なるので、AとBの点数を比較することはできません。
しかし、このIRTを導入することで、Aテストの60点とBテストの80点を、
IRTスコア(同じ基準)に変換し比較することができるようになります。
つまり、テストで出題される問題が異なっていても、受験者集団が異なっていても、
そこで得られた得点は、互いに比較することができるようになるということです。
ただし、このIRTもCBTと同様に、検討課題があり、すぐに導入されるものではありません。
今後、研究が進めば、高校教育でも活用される可能性は十分あります。
まとめ
高校教育改革は、大学入試改革と密接に関係しています。
ひいては、高校教育改革がされるということは、中学校教育・小学校教育も変わっていくということです。
英語教育やIT教育が小学校から導入されるのもその一環です。
このような変化に対応し、「学力の3要素」を身につけることが大切です。
次回は、各大学の個別試験の変化についてみていきます。